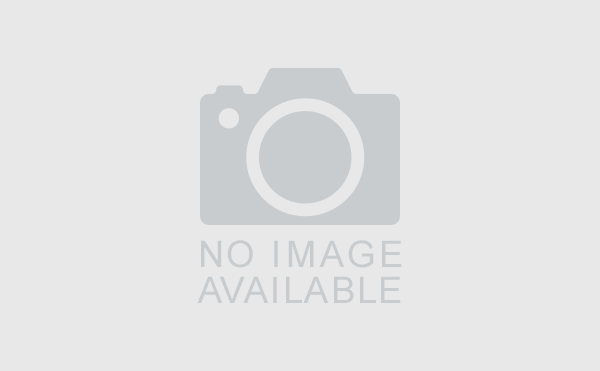きわめて私的な、母の思い出話の2
きわめて私的な、母の思い出話の1より、続き
☆母の思い出話・子供を手放すという事
幸いそれは誤診であったらしいのだが、母の体調は悪化の一途。
当然周囲からは、女手一つの子育てに猛反対される。
しかし、そうなればなるほど猛反発するのが私の母みたいである。
そこに入ってきたのが、母の母、つまり私の祖母、エイだった。
母の兄夫婦には子供が出来なかった。
そこで、本家の跡取りとして和彦を欲しいと言っているという。
また、会いたいときにいつでも会いに来ていいとも。
そこで、兄夫婦と共に暮らす祖母エイが、「私もちゃんと面倒見るから、和彦は兄に渡して、お前はまず体を治すことに専念しなさい。」と説得したという。
「おっかさん(祖母エイのこと)がそこまで言うなら、よろしくお願いします。」と母は私を兄夫婦に渡すことにしたという。
が、そこから兄弟の仲が悪化していった。
原因は幾つかあるが、いつでも会いに来ていいという約束が、無かったことにされたのが最大の理由と母は言ってた。
守られた約束もある。
祖母は人生を懸けて、私を命の最後の瞬間まで守ってくれた。
私の人格の大部分は、祖母から与えられたものだと言い切れる。
その意味で、私はとてもしあわせなのだ。
☆母の思い出話・自立
母はそれから、兄夫婦から親子の名乗りをすることを禁じられ、ただの親戚のおばさんとしてふるまえと指示され、私が辛い目にあわされたら生きていけないと、従うしかなかった。
これは、他の親戚のおじさんおばさんも生前それらしきことを私に伝えていたので、今回、すっきりした。
母は母で、大変だったんだ。
それが分かって、本当に良かったと思う。
私が二歳の時、肺炎で生死の境をさまよった時があった。
病室のベッドをなんとなく覚えている。
セルロイドのピンクの亀の人形を持ってる記憶は、今回正しかったと分かった。
その亀の人形は、母からのお見舞いだったそうなのだ。
でもそれは、意識が回復した時の思い出。
重い肺炎で入院した時、私の意識は無かったそうだ。
母へは、自宅留守番の祖母から連絡が入り、「すぐに駆け付けたんだよ」と言ってた。
「言葉をかけたいけど、なにかしゃべると涙が止まらなくなりそうで、ただじっと手を握ってあげる事しかできなかった。でも和彦は、私が手を握るとギュッて握り返してきたんだよ。」
親子とは不思議なもので、私が握り返したのは母の手だけだったそうである。
そこから母は一念発起。
しっかり自立して、もしもの時にこの子の役に立とうと九州を離れ、神戸で医療の勉強を始める。
沢山の資格を取り、人生の舵を大きく修正していった。
再婚したのは、それから10年後の事だった。
平成の始め、祖母エイが他界する直前、私の母が誰かを教えてくれた。
「恨むなよ、そして機会が有れば連絡を取って、困っていたら助けてやれよ。」
私は、こんな祖母が今でも大好きだ。
そして私は全てから自立し、九州を離れ札幌に来て、日高晤郎ショーに出会った、衝撃だった。
☆晤郎さんへ
晤郎さんからあの日に背中を押されてなかったら。
たまに、そう考えるときがあります。
こうして別々に生きてきた私たち親子が、こんなにも普通に、こんなにも互いの今を尊重し、それでいて昔の少々大変だった時期をしあわせ一杯に語り合えるだなんて。
母から電話が来ました。
誕生日のお祝いが誕生日前日に届いたよとの電話でした。
母の声は、これまでで一番弾んでいました。
有り難うで始まり、有り難うで終わった1時間18分の電話でした。
生きている内に、精いっぱい失った時間を取り戻したいです。
誰も恨んでいません。
だって私はこうして今、充実した人生を送っていますから。
それもこれも、晤郎さんが堂々と人生を語って下さっていたからです。
そしてあの日、惑っていた私の背中に、笑顔で手を添えて下さったからです。
私はあれから、ずっと強くなれたと思います。
有り難うございます晤郎さん。
母85歳、これからはずっと一緒です。
豊平区 和彦